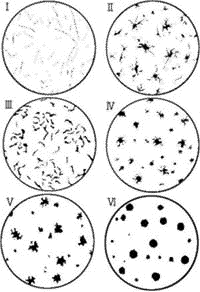鋳物ブログ
球状黒鉛鋳鉄品 JISG5502
1.適用範囲
この規格は、球状黒鉛鋳鉄品(以下、鋳鉄品という。)について規定する。
備考
1.この規格の引用規格を、付表1に示す。
2.この規格の対応国際規格を、次に示す。
ISO 1083:1987 Spheroidal graphite cost iron-classification
2.用語の定義
この規格で用いる主な用語の定義は、次による。
別鋳込み供試材:鋳鉄品とは別個に、原則として鋳鉄品と同種の鋳型を用いて、1バッチごとに鋳鉄品と同一条件で鋳造する供試材。
本体付き供試材:鋳鉄品本体の所定の位置に、原則として鋳鉄品と同種の鋳型を付着させ、鋳造する供試材。
3.種類の記号 鋳鉄品の種類の記号は、表1による
| 別鋳込み供試材による場合 | 本体付き供試材による場合 |
|---|---|
| FCD350-22 | FCD400-18A |
| FCD350-22L | FCD400-18AL |
| FCD400-18 | FCD400-15A |
| FCD400-18L | FCD500-7A |
| FCD400-15 | FCD600-3A |
| FCD450-10 | |
| FCD500-7 | |
| FCD600-3 | |
| FCD700-2 | |
| FCD800-2 |
備考
種類の記号に付けた文字Lは、低温衝撃値が規定されたものであることを示す。
種類の記号に付けた文字Aは、本体付き供試材によるものであることを示す。
4.化学成分
鋳鉄品は、特に指定がある場合、11.4の試験を行い、その化学成分は、受け渡し当事者間の協定による。なお、参考として主な科学成分の範囲を参考表1に示す。
| 種類の記号 | C | Si | Mn | P | S | Mg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCD350-22 | 2.5以上 | 2.7以下 | 0.4以下 | 0.08以下 | 0.02以下 | 0.09以下 |
| FCD350-22L | ||||||
| FCD400-18 | ||||||
| FCD400-18L | ||||||
| FCD400-18AL | ||||||
| FCD400-22L | ||||||
| FCD400-15 | - | - | - | |||
| FCD400-15A | ||||||
| FCD450-10 | ||||||
| FCD500-7 | ||||||
| FCD500-7A | ||||||
| FCD600-3 | ||||||
| FCD600-3A | ||||||
| FCD700-2 | ||||||
| FCD800-2 |
5.機械的性質
鋳鉄品は、11.5の試験を行ない、その引張り強さ、体力、伸び及びシャルピー吸収エネルギーは、表2、表3による。ただし、耐力は、注文者の要求がある場合に適用する。なお、参考として硬さの値と基地組織を示す。
| 種類の記号 | 引張強さ N/m㎡ |
耐力 N/m㎡ |
伸び % |
シャルピー吸収エネルギー | (参考) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試験温度 ℃ | 3個平均 J | 個々の値 J | 硬さ HB | 基礎組織 | ||||
| FCD350-22L | 350以上 | 220以上 | 22以上 | -40±2 | 12以上 | 9以上 | 150以下 | フェライト |
| 種類の記号 | 引張強さ N/mm2 |
耐力 N/mm2 |
伸び % |
シャルピー吸収エネルギー | (参考) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試験温度℃ | 3個平均J | 個々の値J | 硬さHB | 基地組織 | ||||
| FCD350-22 | 350以上 | 220以上 | 22以上 | 23±5 | 17以上 | 14以上 | 150以下 | フェライト |
| FCD350-22L | -40±2 | 12以上 | 9以上 | |||||
| FCD400-18 | 400以上 | 250以上 | 18以上 | 23±5 | 14以上 | 11以上 | 130~180 | |
| FCD400-18L | -20±2 | 12以上 | 9以上 | |||||
| FCD400-15 | 15以上 | - | - | - | ||||
| FCD450-10 | 450以上 | 280以上 | 10以上 | 140~210 | ||||
| FCD500-7 | 500以上 | 320以上 | 7以上 | 150~230 | フェライト+パーライト | |||
| FCD600-3 | 600以上 | 370以上 | 3以上 | 170~270 | パーライト+フェライト | |||
| FCD700-2 | 700以上 | 420以上 | 2以上 | 180~300 | パーライト | |||
| FCD800-2 | 800以上 | 480以上 | 200~330 | パーライトOR焼き戻し組織 | ||||
| 種類の記号 | 鋳鉄品の 主要肉厚 |
引張強さ N/mm2 |
耐力 N/mm2 |
伸び % |
シャルピー吸収エネルギー | 硬さHB | 基地組織 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試験温度℃ | 3個平均J | 個々の値J | |||||||
| FCD400-18A | 30を超え60以下 | 390以上 | 250以上 | 15以上 | 23±5 | 14以上 | 11以上 | 120~180 | フェライト |
| 60を超え200以下 | 370以上 | 240以上 | 12以上 | 12以上 | 9以上 | ||||
| FCD400-18AL | 30を超え60以下 | 390以上 | 250以上 | 15以上 | -20±2 | ||||
| 60を超え200以下 | 370以上 | 240以上 | 12以上 | 10以上 | 7以上 | ||||
| FCD4OO-15A | 30を超え60以下 | 390以上 | 250以上 | 15以上 | - | - | - | ||
| 60を超え200以下 | 370以上 | 240以上 | 12以上 | ||||||
| FCD500-7A | 30を超え60以下 | 450以上 | 300以上 | 7以上 | 130~230 | フェライト +パーライト |
|||
| 60を超え200以下 | 420以上 | 290以上 | 5以上 | ||||||
| FCD600-3A | 30を超え60以下 | 600以上 | 360以上 | 2以上 | 160~270 | パーライト +フェライト |
|||
| 60を超え200以下 | 550以上 | 340以上 | 1以上 | ||||||
6.黒鉛球状化率
鋳鉄品は、11.6の試験を行ない、その黒鉛球状化率は、特に注文者の指定がない場合、80%以上とする。
7.内部の健全性
鋳鉄品の内部には使用上有害な鋳巣などがあってはならない。
8.形状、寸法、寸法公差及び質量
鋳鉄品の形状及び寸法は、図面または模型で指定するものとし、長さ及び肉厚寸法公差は、特に注文者の指定がない場合、鋳造技術標準規定JIS B 0403の球状黒鉛鋳鉄による。鋳鉄品の質量は、受渡当事者間の協定による。
9.外観
鋳鉄品の外観は、使用上有害な傷、鋳巣などがあってはならない。
10.製造方法
鋳鉄品の製造方法は、次による。
鋳鉄品は、キュポラ、電気炉、その他適当な炉によって溶解し、黒鉛を球状化するための処理を行ない、砂型又はこれと同等の熱拡散率をもつ鋳型に鋳造をする。
鋳鉄品は、受渡当事者の協定によって、焼きなまし、その他の熱処理を行なう事ができる。
鋳鉄品は、注文者の承認があれば、製品検査後に補修、塗装、機械加工を行なう事ができる。
11.試験
11.1試験場所
試験場所は、原則として、当該鋳造所とする。
11.2別鋳込み供試材
11.2.1 バッチの構成
1.非連続生産の場合
非連続生産の場合のバッチの構成は、次による。
鋳鉄品は、キュポラ、電気炉、その他適当な炉によって溶解し、黒鉛を球状化するための処理を行ない、砂型又はこれと同等の熱拡散率をもつ鋳型に鋳造をする。
鋳鉄品は、受渡当事者の協定によって、焼きなまし、その他の熱処理を行なう事ができる。
鋳鉄品は、注文者の承認があれば、製品検査後に補修、塗装、機械加工を行なう事ができる。
2.連続生産の場合
同一種類の鋳鉄品(1)を連続して生産する場合は、最大2時間までの出湯量を1バッチとしてもよい。
注(1)同一種類の鋳鉄品とは、表1の種類をいう。
11.2.2 バッチごとの試験回数
バッチごとの試験回数は、次による。
引張試験、黒鉛球状化率判定試験及び衝撃試験は、1バッチごとに各1回行う。
上記によらないで、受渡当事者間の協定によって、連続12バッチ以下をまとめて1グループとし、その中の1バッチでそのグループを代表し試験をする事ができる。ただし、この場合には、黒鉛球状化処理が毎回確実に行われたことを顕微鏡組織試験、非破壊試験、破面試験、その他の方法を用いて確かめなければならない。
11.2.3 供試材の製造方法
供試材の製造方法は、砂型を用いて、1バッチごとに鋳鉄品と別個に、鋳込みの終わり近くに鋳造をする。鋳鉄品が鋳型内で黒鉛球状化処理される場合は、供試材も同じ方法で鋳込む。供試材の数は、予備を除き1個とする。ただし、FCD350-22、FCD350-22L、FCD400-18及びFCD400-18Lについては衝撃試験用供試材として1個追加してもよい。
また、熱処理を行う場合には、原則として供試材は、鋳鉄品と同一炉で同時に熱処理を行う。
11.2.4 供試材の形状及び寸法
供試材の形状及び寸法は、図1及び表4のY形のA号~D号並びに図2のノックオフ形(Ka形又はKb形)の6種類とし、原則としてY形のB号を用いる。この場合、Y形のB号の代わりにノックオフ形(Ka形又はKb形)を用いてもよい。
また、受渡当事者間の協定によって、Y形のA号、C号、D号のいずれかを用いることができる。
なお、供試材の種類は、試験成績に付記する。
図1 Y形供試材の形状お世費製造方法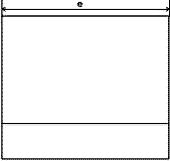 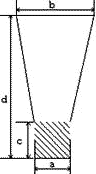 |
表4 Y形供試材の寸法(単位mm)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 供試材に用いる砂型の厚さはA号及びB号では40mm以上、C号及びD号では80mm以上とする。
図2 ノックオフ形(Ka形,Kb形)供試材及び鋳型の形状及び寸法(単位mm)
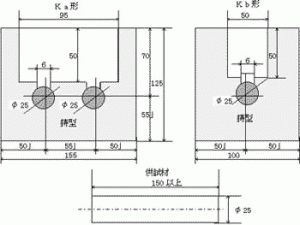
11.3本体付き供試材
11.3.1 バッチの構成
1個の鋳鉄品を1バッチとする。
11.3.2 バッチごとの試験回数
引張試験、黒鉛球状化率判定試験及び衝撃試験は、1バッチごとに各1回行う。
11.3.3 供試材の製造方法
供試材は、鋳造品本体に付けて鋳造する。鋳造品1個の質量が2,000kg以上で、主要肉厚が30~200mmの場合には、受渡当事者間の協定によって別鋳込み供試材の代わりに本体付き供試材を選ぶことができる。供試材を本体に付けるときの位置決めは、受渡当事者間の協定による。
本体の鋳鉄品が熱処理を必要とする場合には、熱処理を終えるまで供試材を本体から離してはならない。
11.3.4 供試材の形状及び寸法
供試材の形状及び寸法は、図3及び表5による。
図3 本体付き供試材の形状及び寸法
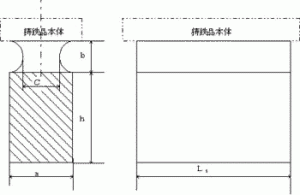
| 鋳鉄品の主要肉厚 | 寸法 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | h | Lt | |
| 30を超え60以下 | 40 | 30以上 | 20以上 | 40~60 | 150以上 |
| 60を超え200以下 | 70 | 52.5以上 | 35以上 | 70~105 | 150以上 |
備考 寸法を減らすことを協定する場合には、次の関係を満足させるものとする。
| b≧0.75a 及び c≧ | a |
| 2 |
11.4分析試験
11.4.1 分析試料
分析試料は、供試材を採取するごとに1個採取する。ただし、炭素分析の試料は白銑試料から採取しなければならない。
11.4.2 分析方法
分析方法は、原則として、次のいずれかによることがある。
JIS G 1211,JIS G 1212,JIS G 1213,JIS G 1214,
JIS G 1215,JIS G 1253,JIS G 1256,JIS G 1257
11.5機械試験
11.5.1 試験片
試験片は、次による。
引張試験片は、JIS Z 2201の4号試験片を図1、図2又は図3の供試材の斜線を施した部分から採り、その数は予備を除き1個とする。
衝撃試験片は、JIS Z 2202の4号試験片を図1、図2又は図3の供試材の斜線を施した部分から採り、その数は予備を除き3個とする。
硬さ試験片は引張試験片の一部を用いる。
- 引張試験片は、JIS Z 2201の4号試験片を図1、図2又は図3の供試材の斜線を施した部分から採り、その数は予備を除き1個とする。
- 衝撃試験片は、JIS Z 2202の4号試験片を図1、図2又は図3の供試材の斜線を施した部分から採り、その数は予備を除き3個とする。
- 硬さ試験片は引張試験片の一部を用いる。
11.5.2引張試験方法
引張試験方法は、JIS Z 2241による。
11.5.3衝撃試験方法
衝撃試験方法は、JIS Z 2242による。
11.5.4硬さ試験方法
硬さ試験方法は、JIS Z 2243による。
11.6黒鉛球状化率判定試験
- 試験片
試験片は、図1、図2又は図3の供試材の斜線を施した部分から1個採る。- 試験方法
試験方法は、顕微鏡組織写真又は直接観察による黒鉛組織について行う。- 黒鉛粒の形状分類
黒鉛粒の形状分類は、図4(ISO 945FIGURE1.による)のとおりとし、これに基づいて黒鉛粒を分類する。- 黒鉛球状化率の算出
顕微鏡組織における黒鉛球状化率の算出は、次による。
- 倍率は原則として100倍とし5視野について行い、平均値を求める。
- 2mm(実際の寸法20μm)以下の黒鉛及び介在物は対象としない。
- 図4の形状Ⅴ及びⅥの黒鉛粒数の全黒鉛粒数に対する割合(%)を求め黒鉛球状化率とする。
- 画像解析処理によって算出する場合には、(3)に準じて行う。
- 受渡当事者間の協定による標準組織写真がある場合には、これを用い、5視野の組織を比較して球状化率を判定してもよい。ただし、この場合の標準写真の黒鉛球状化率は、11.6.3によって黒鉛粒の形状を分類し、11.6.4(1)~(4)の方法で求めたものとする。
図4 黒鉛粒の形状分類図
11.7再試験
再試験は、次による。
- 試験片のきず又は鋳巣が試験成績に影響を及ぼしたと判断したときは、その試験を無効とし、予備の試験片を用いて再試験をすることができる。
- 引張試験又は衝撃試験の成績の一部が規定に適合しない場合は、規定に適合しない試験について予備の試験片を用いて再試験を行うことができる。その場合の試験片の数は、11.5.1の試験片の数の2倍とする。ただし、2倍の試験片が採取できない場合は、受渡当事者間の協定による。
また、再試験の成績は、すべて5.及び,6.に適合しなければならない。- 試験成績が5.及び6.に適合しない原因が熱処理によるものと認められる場合は、予備の供試材を用いて、11.2.3又は11.3.3によって再熱処理を行い、再試験することができる。この場合、試験片の数は(2)によらないものとし、再試験は11.5及び11.6によって行い、5.及び/B>6.に適合しなければならない。たたし、再熱処理回数は2回までとする。
12.検査
鋳鉄品の検査は、次による。
- 機械的性質は、5.に適合しなければならない。
- 黒鉛球状化率は、6.に適合しなければならない。
- 内部の健全性は、7.に適合しなければならない。
なお、健全性の合否判定基準は、必要がある場合、受渡当事者間の協定による。- 形状、寸法、寸法公差及び質量は、8.に適合しなければならない。
- 外観は、9.に適合しなければならない。
- 鋳鉄品は、検査前に塗装その他、検査の妨げになる処置を行ってはならない。
13.表示
表示は、製品又は1包装ごとに次の事項を表示する。ただし、注文者の承認を得た場合は、その一部を省略する事ができる。
- 種類の記号
- 製造業者名又はその略号
- 製造番号又はその記号
14.報告
製造業者は、注文者の要求がある場合、製造番号を記載した試験成績書を提出する。
付表1 引用規格 JIS B 0403 鋳鉄品―寸法公差方式及び削り代方式 JIS G 1211 鉄及び鋼―炭素定量方法 JIS G 1212 鉄及び鋼中のけい素定量方法 JIS G 1213 鉄及び鋼中のマンガン定量方法 JIS G 1214 鉄及び鋼中のリン定量方法 JIS G 1215 鉄及び鋼―硫黄定量方法 JIS G 1253 鉄及び鋼―スパーク放電発光分析方法 JIS G 1256 鉄及び鋼の蛍光分析方法 JIS G 1257 鉄及び鋼―原子吸光分析方法 JIS Z 2201 金属材料引張試験片 JIS Z 2202 金属材料衝撃試験片 JIS Z 2241 金属材料引張試験方法 JIS Z 2242 金属材料衝撃試験方法 JIS Z 2243 ブリネル硬さ試験方法 ISO 945 Cast iron―Designation of microstructure of graphite